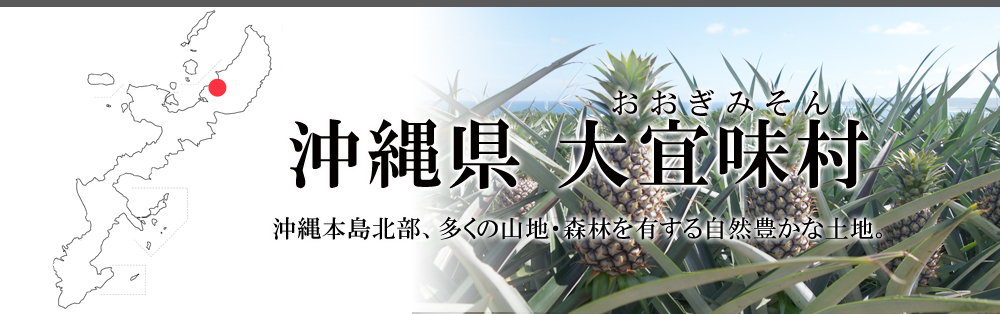沖縄北部の町「大宜味村」の山奥の原生林かと思ってしまうような、ジャングルの中を切り開いたようなシークワーサーの農園がありました。
農園を案内してくださったJAおきなわ・シークワーサー指導員の照屋さんは大宜味村のご出身で、シークワーサーを育てている90人ほどの農家さんとコミュニケーションを取りながら、より良いシークワーサーを楽しんで頂こうと奮闘されていました。
今の1番の問題は後継者不足。
シークワーサー農家さんの平均年齢が86歳というものの、まだまだみなさん元気いっぱい!
が、やはり若い後継者が欲しいなぁと言うのが本音だそうです。
今回、照屋指導員にご紹介頂いたのは、お父様の代からシークワーサーを育てていらっしゃる小橋川さん。
たまたまお伺いした日がお誕生日で68歳に成られたばかりでした。
小橋川さんのこだわりは、除草剤を使わずに手作業で雑草を取り除き、ふかふかの土壌を作ること。
ふかふかの土壌が出来れば、シークワーサーの木がしっかりと根を張り、とってもジューシーで栄養が豊富な実を付けるそうです。
小橋川さんの農園で一番古い木は100年の樹で、しっかりと大粒な実を付けていました。
お父様から農園を受け継いだ頃にはまだ電気も車が入れる道路もなく、手作業で収穫されたシークワーサーは大きなカゴに入れて小橋川さんが担いで山を降りたそうです。
数年前にやっと風力発電の風車が近くに作られて電気が通ったそうです。

農園を見て回っている時に注意されたのが所々にある小さな窪み。
「足を取られないようにね~」とのご注意でしたが、これは何ですか?と聞くと、イノシシが収穫前になると実を食べに来て、あちこち荒らしてしまうんだーと話していました。
血糖値を下げる効果があると言われ、一時は大ブームとなったシークワーサー。
沖縄では「平実檸檬(ヒラミレモン)」と呼ばれ、年が明けた1月~2月ごろには、完熟してオレンジ色になったシークワーサーも美味しいよ!
また機会があったらその頃に食べに来なさい。と、小橋川さんのにっこり笑う笑顔がとても素敵でした。